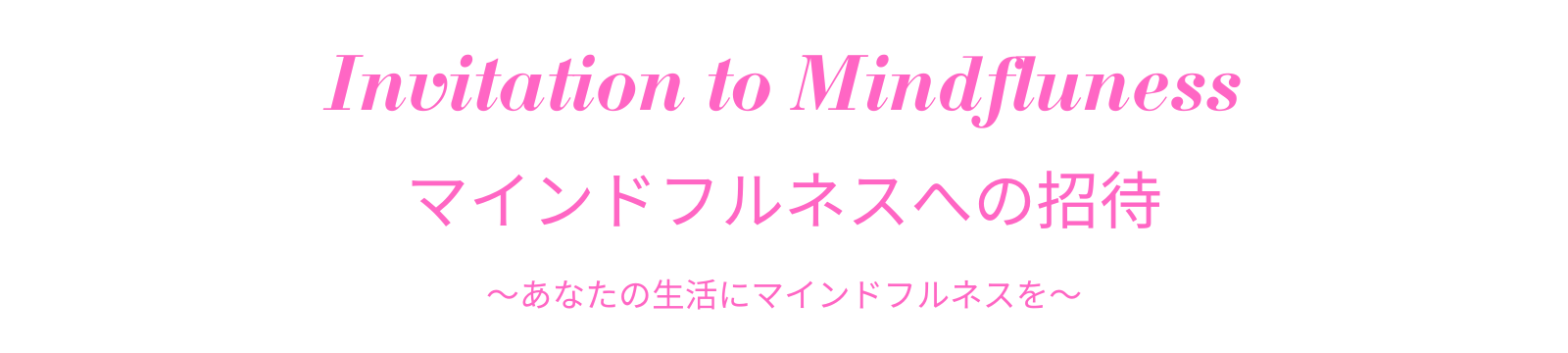不退の行法
関西の本格的な春の訪れは、東大寺の修二会の「お水取り」が終わらないとやって来ないと言われています。
先日、東大寺長老の筒井寛昭さんに東大寺修二会「不退の行法」について、お話を聞く機会がありました。寛昭さんは、やさしい面持ちの小柄な方で、今年80歳になられるそうです。
お話によると、「不退の行法」と言われる修二会(「お水取り」)は、1274年もの間(2025年現在)、数々の戦乱や自然災害が起こる中も一度も絶えることなく、鎮護国家、天下泰安、風雨順時、五穀豊穣、万民快楽など人々の幸福を願い、連綿と今日に至るまで引き継がれて来ました。
また、日本では古くから金峯山寺等を中心とした自然の中で修行する修験道が広く行われており、その後、神道と仏教が1300年の間に神仏習合していったそうです。
修二会は、その起源とされる実忠和尚から真言宗の空海(四国八十八か所)に至るまで、「自然の中で修行する」という日本の文化・伝統の中、鎌倉時代に現在の形になったそうです。
次に寛昭さんは笑顔で「あなたは昨年噓をつきましたか?」と私たちに問われました。
「一度も嘘をつかなかった人なんていないだろう。」とだれもが心の中で思っていたのか、場内に笑いが起こりました。
「けどね、それは罪になるんですよ。それはやはり「噓をつきました」と懺悔して、悔い改めるための行を行わないとあかんのです。しないと嘘で固まって、違うところに行ってしまうからね(笑)。修二会は悔過(けか)法要と言って、懺悔して心を浄めるための法要なんですよ。」と優しく私たちを修二会の世界に誘われます。
修二会の起源となった実忠和尚は、笠置山の龍穴で天界のすばらしい行法を垣間見て、この行法をぜひ人間界に遷したいと願い始められたそうです。
私が驚いたのは、寛昭さんが「日本人は感覚として、人間界と天上界という次元が異なっている世界があること、人間とはまた異なる人がいるということやその人たちとの繋がりを感じる心を持っていたのですよ。浦島太郎もいっしょでしょう?」とおっしゃったことでした。
私は、あらためて当時の人の見えないものを感じる力や、その力で人の幸福に繋がる確かなものをどのように取り入れたらよいかということを直感的に感じ取る感性と人の心への深い洞察に驚きました。
また、寛昭さんは「「仏が、仏が…。」とばかり言うのはちがうでしょ。」ともお話されていました。


心の系譜
修二会の、神道による最初のお浄めは、宮司による「かまど」のお浄めです。そうして、口に入るものを浄めます。仏教行事ではありますが、昔からおられる神様を大切にしているとのことです。
そして、仏教としての「悔過法要」が始まります。それは、私たちが十一面観音様に助けを求めるだけではなく、まず最初に自分の行動を悔い改めることが基本だそうです。
「神名帳の読み上げ」は、神様、仏様の名前を読み上げます。大菩薩、大明神等、522柱の神々を序破急の構成で音楽のように読み上げます。
次に13700余所の「有官知(うかんじ)」という私たちが知っている神々、「未官知(みかんじ)」という私たちが知らない神様、そして、御霊(ごりょう、元は祟り神、恨みを持って死んだ人等 例:菅原道真)の名前を読み上げます。
また、「過去帳の読み上げ」では、東大寺建立を発願した聖武天皇や初代別当の良弁僧正、後白河法皇、源頼朝などの歴史上の錚々たる人たちの名前が読み上げられるのですが、鎌倉時代に「青衣の女人(しょうえのにょにん)」が現れて、「なぜ私の名前を読まないのか」と言ったそうです。
寛昭さんのお話では、「「青衣の女人」というのは、身分の低い女性や子ども等弱い立場の人も含めて、その存在を認識してほしいということで現れたのではないでしょうか?その昔、大仏を作るのに、一握りの土を寄せあって老若男女が作ったのに、そんな人たちにも思いをはせて、読み上げてくださいよということだと思います。
世界にはいろんな人がいて、それぞれ違う環境があり、我々が知らん神様もいっぱいある、けれどちゃんと相手の人格を認め、敬う、もののけ姫の「猪」も同じです。「猪」やけれど天地を動かせるぐらいの力を持っていると認めている。菅原道真に対しても、我々のためにちゃんとしてくれた人なのにこのままでよいのか…。と思ったのでしょうね。日本人としての1300年間の考え方は、たとえ喧嘩をしてても相手を認めて、相手のことを思う。決して殺して終わりではないのです。そうすることによって力を貸してくれることもあるでしょう?」とのことでした。
私は、「ああ、なんて深い教えなんだろう…。でもどれほどの命がこの智慧を得るためにその代償となっていったのだろう…。だから修二会は続けていかなければならなかったのだろうなあ…。」と感じました。
また、ふと「慈悲の瞑想」で自分の苦手な人に対しても、もし可能なら、その人の幸せや健康を願うことを思い出しました。
とても難しいですが、もしそのように心のスペースがほんの少しでも出来て、相手の立場を思ったり、感謝したり、敬う気持ちを持つことが出来るのなら、もしかしたら私たちの未来も何かが変わっていくかもしれない…。とも感じました。
火と水と地に生きる人間
「水取行法」は、神名帳の読み上げに遅参した遠敷明神が若狭の聖水を送り、それを本尊に捧げたのが始まりだそうです。
「この行法の中では、陣内に柳を生けています。柳の枝は生命力が強く、切ったら水が出るので、水道管の象徴のような役割として、これが日本全国に伸びていくようにと祈りを込めているのではないでしょうか?日本では飢饉で亡くなった方が多かったからです。」と話されていました。
修二会のクライマックスは、「達陀(ダッタン) 行法」です。これは「火の行法」で、二月堂の堂内で大松明を打ち振り、引き廻し、私たちすべての煩悩、罪や汚れを焼き尽くさんとばかりに火の粉を散らせながら駆け巡ります。
お話によると、民間信仰としての要素もあるそうで、火天は、野焼きを意味し、土に養分を与えます。水天は、若水を汲み、土に撒き与え、芽の出るように環境を整え待ちます。そして、「ダダオシ」として両足で、大きな音を立て、悪霊を踏み鎮めるのと同時に、「種よ!早く起きて芽を出してくださいよ!」という意味があるのだそうです。
そして、寛昭さんはそのお話の最期に「一切の衆生に代わって、旧年中に犯した罪や過ちを悔い改め、新しい年の平安と安穏を祈る行事が東大寺修二会です。どうぞこの行事を見ることによってご自分の罪や汚れを祓い清め、悔い改め、そして、自分の幸福だけでなく、生きとし生けるものが幸せであるように祈ってください。」と結ばれました。
私は、19時からお松明が始まるのを待ってました。そこには、日本人だけではなく、世界中から様々な人たちがその法要を見に来ていました。行法の説明も日本語、英語、中国語で行われます。修二会の指揮をとられた実忠和尚は東大寺を開山した良弁僧正の高弟のインド僧であり、その当時も国際色豊かなお式だったとの事です。
大松明が赤々と燃え、大きく上下に振られます。舞い上がる火の粉が飛んでくる様子を見ながら、まず、呼吸しながら今、ここにいることを感じます。大松明の光と熱が冷えた体に伝わってきます。心の中で、まず嘘をついた事や怒ったこと等を思い出し、「ごめんなさい。今年はなるべくしないようにします…。」と誓い、「慈悲の瞑想」唱えました。
光明熾盛照十万 光明ははなはだ盛んに十方を照らして
摧滅三界魔波旬 三界の魔王波旬を摧き滅す
抜除苦脳観世音 (衆生の)苦悩を取り除き給う観世音菩薩
普現一切大紳力 普く一切の大神力を現じたまうなり
(十一面悔過「散花」より)
火の行法を観ていると、私の中の穢れが火に焼き払われ、身体が軽くなってていくようにも感じました。
「ああ、もうすぐ春…。これでやっと春が迎えられる。」となんだか嬉しくなりました。
ご興味を持たれた皆さん、お松明は3月14日まで毎日上げられ、毎年、12日、最も大きな松明の「籠松明」行われるそうです。
もし良ければ、春を迎えに行ってみませんか?