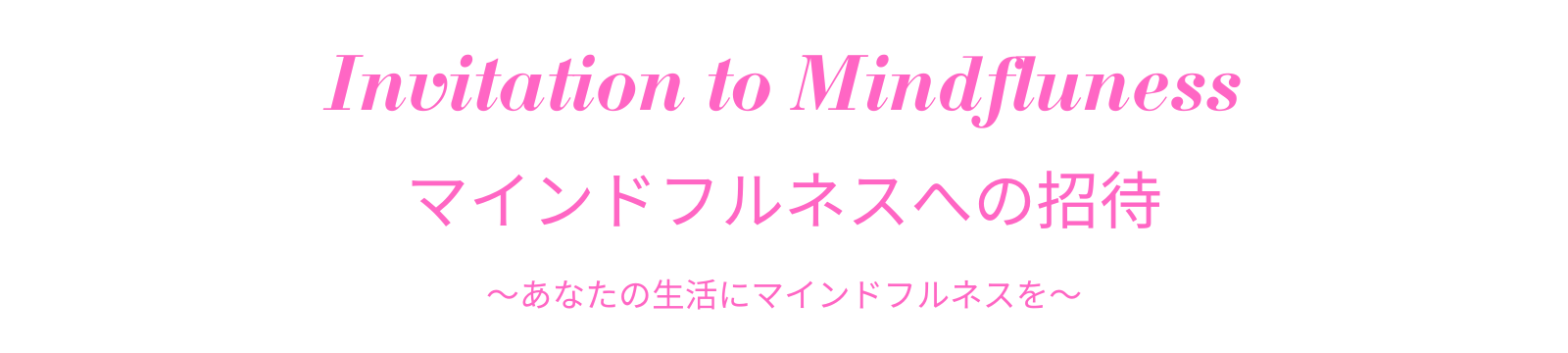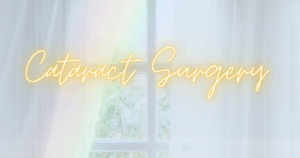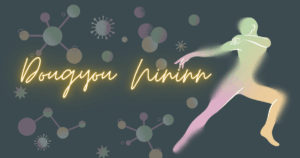Beyond Emotional Intelligence
そんなうまい方法が果たしてあるのだろうか?
MBSR(マインドフルネスストレス低減法)講師のために、MBSR研究会が継続学習会を立ち上げてくれました。
その学習会では、アメリカのMind&Life Podcastという瞑想科学の最先端の方々がウェンディ・ハセカンプさんの司会をする番組「mind &life」でのとても興味深いインタビューの中から、自分たちが関心のある回をひとつ選び、英語逐語訳をAIで日本語に翻訳し、この会で発表します。
どの回もとても興味深い番組で、私たちは、多くのことが学べます。
今回は、ダン・ゴーレマンさんの「Daniel Golemem~Beyond Emotional Intelligence~ 」です。
私は、発表の途中まで気が付かなかったのですが、日本では、ダニエル・ゴールマンさんとして30年くらい前に「EQ~こころの知能指数~」が一大ブームになっていました。
私は、「あっ、この本持っていたわ。」を本棚を探すと、30年前の領収書が挟まっており、この方もまた瞑想の実践と研究を深めておられたのかと嬉しくも不思議に感じました。
彼の研究に関しては、「マインドフルネスストレス低減法」の本の中でも以下のように紹介されています。
「ウィスコンシン大学のリチャード・デビッドソン博士らと共同で、ストレスを感じている従業員を対象として、企業での勤務時間にマインドフルネスストレス低減法を実施し、その効果を検証しました。
その結果、参加者は、8週間プログラムの間、参加しなかった人たちと比べて感情の表出と関係する前頭前野の部位に変化が生じたことが判明しました。
つまり、瞑想をした人達は、そうでない人達よりも、不安や落ち込みといった感情にうまく対処しており、いわゆる「心の知能指数」(Emotional Intelligence: CE)が高くなったことが示唆されました。」
(マインドフルネスストレス低減法 J.カバットジン 春木豊訳 北大路書房 十五周年記念版の序文 xixより抜粋)
マインドフルネス瞑想を支える支柱の一つが、初期から「科学」に裏打ちされたものであることがうかがえます。
話を戻しますが、Mind &Life Podcastのオープニングを訳すと、「人生をどうやっていくかには方法がある」と始まり、“感情的知能の4つの基本は、(1)自己認識、つまり自分が何を感じているか、それが自分の知覚や思考をどのように形成しているかを知ること、(2)自分の破壊的な感情を管理し、生産的な感情を動員すること、次に(3)共感、つまり誰かが言葉でなく、非言語的なもの、声のトーン、顔の表情などで何を伝えているかを読み取ること、そして(4)これらすべてを組み合わせて効果的な人間関係を築くことです。”とのことでした。
まさに、MBSRと方向性は同じです。そして、ゴールマンさんは、「人生をどうにかやっていく方法」として、「感情」に焦点を当てて、瞑想科学と感情的知能をつなぎ、さらに探求されていたようです。
「ただ気づいておくだけ…」
マインドフルネス瞑想では、最初はその人にとって差支えがない場合は、呼吸に意識を向ける注意・集中のプラクティスから始めますが、少しずつ意識を向ける対象を広げていきます。
「瞑想での、私たちの意識の体験領域は、「意識の三角形」とよく言われます。三角形の3つの頂点は、自己認識の3つの構成要素である、⑴身体感覚や感触、⑵感情や気持ち、そして⑶思いや考えであり多くの意味で人間の体験を構成しています。」(マインドフルな大学生 エリック・ラウクス著 伊藤清、渋沢田鶴子翻訳研修 金剛出版 pp.40より引用)
この⑵の感情や気持ちは、何かの思い出や経験に付随して、私たちの意識に立ち現れてきます。
その時に大切なことは、立ち現れた感情や気持ちに対して、こんな風に思ってはいけないと自分を責めたり、無理に抑え込もうとしたり、何でもないことのように無視をしたりしないで、「ただ気づいておく」ということがとても大切な一歩になります。
感情を観察する
「自分で評価を下さないこと」がマインドフルネス瞑想の9つの態度(以前は7つでしたが、今は感謝と寛容が追加されました。)の一番最初に出てきます。
この態度は、本当に私たちの心を自由にしてくれる最初の一歩になります。
私がブラウン大のMBSRの講習を受けた時、フローレンスさんが、よく「Just noticing and …」とおっしゃっていました。
そして、例えば、MBSRを毎週受けていくと、私たち自身が本当に今この瞬間に何を感じ、何を考え、そして自分とはどういうものか、人とは…?世界とは…?と意識は、様々なことにつながり、そして、広く深い探索が始まる人もいるでしょう。
そのような中で、時間を少し経て、瞑想の中で、何度もその感情に出会い、できるだけ巻き込まれずに、「優しくそこにいてもいいよ。」という気持ちで観察を続けていると、その感情がなぜこの瞬間に立ち上がってきたのか、その感情の意味することが、自分の中ではどういうことだったのかなど心の底から納得できたり(腹落ちしたり)するかもしれません…。
そして、その感情があったからこそ、私たちは今この瞬間にここにいるのかもしれません…。
そのように自分に対する理解が深まると、もしかしたら、自分に対する慈しみの気持ちや「よくがんばってきたね…。よく生き抜いたね、しかたないよ。人間だもの…。ありがとう等」の感謝の気持ちを持つこともあるでしょう。
その結果、巻き込まれていた感情と自分とは、別もものであり、自分と感情の間にほんの少しかもしれませんが、スペースができ、そのスペースの中で新たなマインドフルな選択が可能になってくるかもしれません。
「ただ気づいておくだけ…。」
こんな簡単なことが、自分の感情を探索し、対処するための大切の入り口になります。
(でもやってみるととても難しく、よく巻き込まれるのが普通です…。人間だもの!)
みなさんにも、こんな「感情との付き合い方」があることを知っていただけたら嬉しいです。
そんな時は、まず、自分の状態について相談できる枠組みの中で始めることをお勧めします。
瞑想中に立ち現れてくる感情には、人生の様々な経験の中で思い出したくない感情も現れることがあり、そのような感情に強くまきこまれてしまったりすることも、時にはあるからです。
まだまだ酷暑が続くようです。秋が待ち遠しいです。どうぞ体調にはくれぐれも気を付けて過ごしてくださいね。