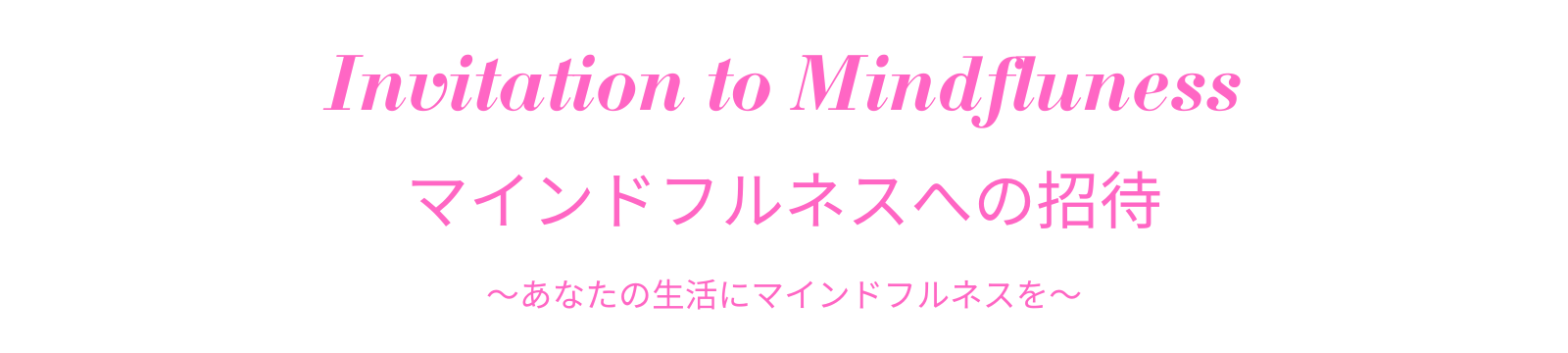大阪の美しい財産
先日、大阪府中之島図書館のガイドツアーに参加しました。
私が生まれる前からそこに存在していた、高校生の時は友人が夏休みに受験勉強に通っていた、車に乗るようになってからは、「きれいだなあ。」と高速道路から眺めていた…、でも実際に中に入ったことはなかった…、長い間、その存在は知ってはいたが、なぜだか、ずっと通り過ぎてばかりだったこの美しい未知の建物…。
ツアーコンダクターの方の話を驚くようなことばかりでした。
まず、正面の入り口の前に立ち説明を聞きました。
このギリシャ風の重要文化財である建物は、1904年(明治37年)に建てられ、その建設のために、第15代住友吉左衛門友純(ともいと)氏が現在の40億円にもあたる額を寄付をしたこと、戦火や自然災害に何度も会いながら生き残った建物であること、正面の4本のコリント式円柱は愛媛県大島の石、建物には岡山県北木島の石を水路で運んでいた可能性があること、釘や接着剤はほとんど用いず、図書館自体は、自重でその存在を支えてきたことなどその歴史が語られました。
まるで、エジプトのピラミッドと同じだなあと感じました。
少し角度をずらして建物を見ると、大きな煙突が左手に見えます。当時のボイラー室が現存して、120年以上も経ちますが、今も現役で冬には間の部屋を暖めるために活躍しているそうです。
美しいグリーンのドームにはステンドグラスがはめられ、雨樋までも住友家の縁の深い銅で作られ、ていねいに何度も修復されているそうです。
「ああ…、今もこの図書館は生きているんだなあ。」という感覚が沸き起こりました。

女神に願う
正面から内部に入ると、右手に明治36年(1903年)の上棟式の「棟札(置札)」が飾られており、罔象女神(みつはのめのかみ)に、この大工事に関わる人々の安全を祈願されています。
罔象女神は、日本における代表的な水の女神(水神)です。
当時の人々は、日本の近代化を第一に優先し、日本古来の神様なんて、軽視していたのではないかと思っていました。
けれども、自然や目に見えないものに畏敬の念を感じ、女神様に祈っていたのだと思うと日本人の中に脈々と流れている自然に対して真摯に祈りを捧げる姿に驚きました。水都大阪に、長い間、風雪に耐え、大阪の糧となるような図書館を建てるという強い願いが感じられました。
ホールに入るとなぜだか分かりませんが、自然と身が引き締まる感覚を感じました。
立ち止まり、呼吸に意識を向け、深呼吸してみました。内部の空気はしっとりと暖かい感じがします。石だけではなく、日本らしく美しい光沢のある木材も使われおり、壁の石との調和が感じられました。
周囲をゆっくりと見まわすとホールの天井には、美しいステンドグラスがはめられています。天から降り注ぐ優しい光がホールを照らしています。それは、まるで教会のようでした。
その美しいステンドグラスの下に立って、その中心を見つめてみました。
そう長い時間ではなかったのですが、何か目のようなものが私を見ているような感覚がして、クラクラとしました。
階段をゆっくり上っていくと、額が掲げられており、その両脇には野神像と文神像と八人の賢者の銘が並んでいます。
これらを見上げながら、この階段をさらに上がっていく時の厳かな感じは、まるでエジプトの神殿の中に入っていくような、また神社に向かう長い階段を上っていくような、とても厳かな気持ちを感じました。



図書館の起源
展示されていた図書館の平面図を見ると、十字の形で、ちょうど両手を伸ばして大地に人が立っているのを、空の上から見たように感じたことや、自分がホールのステンドグラスを見上げている姿がちょうどこの平面図とフラクタルのように感じました。
あまりにこの古い図書館の中での経験が印象的だったので、「大阪中之島図書館、建築」というワードで検索してみました。すると、「住友吉左衛門と大阪府立図書館」という論文が見つかりました。建築家は、野口孫市氏でその師は辰野金吾氏とのことでした。
その第6章に、「岡田温氏の『図書館』によると、(前略)図書館の始まりは、…(中略)古代図書館として名高いのがアレクサンドリア大図書館である。アレクサンドリア大図書館が完成したのはプトレマイオス二世フィラデルフォス(308-246BC)の時代であり、ムーサ(ギリシア神話で学問、芸術をつかさどる女神)を祀った神殿ムーセイオンに付属してこれが設けられる。(中略)つまり、図書館は神殿という神聖な領域に置かれ、日常の場所から一段高いところに作られているのであり、日常性から脱するある精神性が図書館に存在していたことがここに推察されるのである。(後略)」と図書館というものの興味深い由来が説明されています。「住友吉左衛門と大阪府立図書館」第6章p.21より引用
ああ、この図書館は、もしかしたら、神殿のように人間が天とつながり、その「知」を頂く神聖な場所として、建築家の野口氏により具現化された精神性の高い建物だったのだなあと感じました。
その意図、大いなるコンパッション
そして、この図書館の建設の意図を友純(ともいと)氏は、階段を上がった正面に掲げられている建館寄付記(大銅板額)に「(大阪の)市民のための便益をはかり、子弟(大阪の子どもたち)の教育を助ける施設の欠如をかねがね痛感していて、このための資を投ずる機会を待ち望んでいたことである。もう一つは住友が大阪の地で財をなし、これに報いるためである。」と述べておられます。「住友吉左衛門と大阪府立図書館」第3章p.16より引用
住友吉左衛門友純氏の大いなる意図は、自分の利益や名声だけを求めるものではなく、自分が受けた豊かさへの感謝と報恩、まだ豊かさが届いていない人々への慈しみの心の現れであったのかもしれません…。
長い歴史の中でその時代に人々の中に息づき、育まれた「知」の蓄積の歴史が、中之島図書館として水の都、大阪に、神殿のように厳かであるけれども同時に人への温かさを感じる建物として今も佇んでいました。
私は大切にその面影と歴史とハートを心に留めました…。
ツアーに誘ってくれたみなさん、ありがとうございました。
きっと、みなさんの身近にも先人の方が、私たちの想像をはるかに超えたすごい志を持って残された贈り物がたくさんあるはずです。
冬の来る前に、日常の忙しさの中で、少しSTOPして感じてみませんか?